胸を張るだけでは間違い!?「巻き肩」の改善について
大前提として、「巻き肩」は胸郭出口症候群や四十肩・五十肩、親指の腱鞘炎の原因の一つになります。これらの改善と予防の為に「巻き肩を正したい方向けの記事」になります。(美容目的の施術は、開院の動機に反すので致しません)
「巻き肩」は治るのか?
結論から言うと治ります。
※鎖骨の骨折・脱臼経験のある方は難しいかもしれません。
「巻き肩」は単に「巻き肩姿勢の時間が多い」ことを意味しています。端的に言うと、これを正すには「施術で正して、日常生活で意識する」だけです。でも、デスクワークでそれが現実的に困難。美容師でいつもドライヤーやカラーの際に片手が前に出ている姿勢にならざるを得ない。等の場合には机上の空論を言っていても巻き肩にとっては何の意味もないでしょう。だったら、定期的に正すことで「巻き肩状態で固まらない様にする」ことを当院ではお勧めしています。
巻き肩の程度について
仰向けに寝た際に肩がベッドや床に「ピタッとつく」事が正しいと思われている方がいます。もしかしたら「美容的にはそれが正しいと推奨している方がいるのかもしれません」。でも、私の個人的な持論ではなく医学的・解剖学的には全く違います。ベッドや床の面に対して肩が35度位は前に入っているのが正常です。冒頭に述べたような症状の改善・予防に必要な巻き肩の改善には医学的・解剖学的に正しいことが前提です。
巻き肩の解釈の違いの理由
肩甲骨は、「平面上」ではなく「円柱状の」胸郭(肋骨などが作る籠状のもの)に面しているものです。想像して下さい。平面の壁に衣服を掛けたのと、円柱状の壁(柱)に衣服を掛けた際にどちらが壁と衣服の密着度は高くなるでしょうか。私は、円柱状の面に硬い骨である肩甲骨が「ピタッと接することはない」と考えています。
「巻き肩」と肩以外の部分との関係性
巻き肩なのか、猫背なのか。背中だけ丸い猫背なのか腰から丸い猫背なのか。右肩が巻き肩なのか、左が胸を張り過ぎなのか。「どこにフォーカスするか?」で見方は変わると思います。大事なのは、「木を見て森を見ず」では医学的な改善には繋がらないということです。極論、巻き肩を正せば姿勢は良く見えます。でも、後にその皺寄せは他の部分の症状を引き起こすリスクとなります。具体的には、腰を反らすことで巻き肩を正して脊柱管狭窄症・膝やふくらはぎの後面の痛みを引き起こしたりすることが多いです。だから、「巻き肩をどう正すか?」よりも「巻き肩の為にどこを正すか?」が大切だと思います。
四十肩・五十肩に関するその他の記事

「左右の肩の高さが違う」のはカバンや荷物を同じ側に掛けるせい??
☑鏡を見ると肩の高さが左右で違う。 ☑肩こりに明確な左右差がある。 ☑四十肩や五十肩を良くしたい。 ☑四十肩や五十肩になりた...

根本治療・根本改善の混同されがちな“2つの意味”と“こり”について
根本治療、根本改善。 これには2つの解釈があると私は考えています。 ①再発せずに効果が長期に続く。 ②効率よく効果が出る。 これは、似て非なるものだと考えています。 ど...

テーピングをする意味と価値について
私は当然ながら医師ではないので、患者様の症状に対して用いることが出来る武器が非常に限られています。 ・自分の手 ・自分の頭 ・ベッド ・テーピング ・アイシング用の保冷...
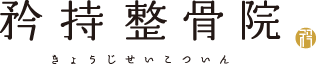
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00-12:00 | |||||||
| 16:00-21:00 |
- 水(第2, 4, 5)は午後休診
- 土は14:00まで
ご予約・お問い合わせはこちらから
03-3714-3855